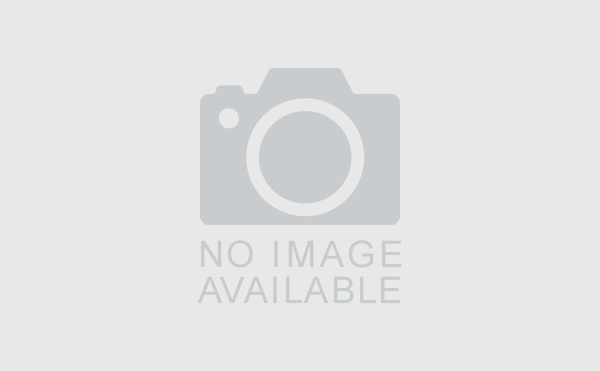トマトのこと
おはようございます
こんにちは
こんばんは
あなたはこの本をご存知でしょうか?
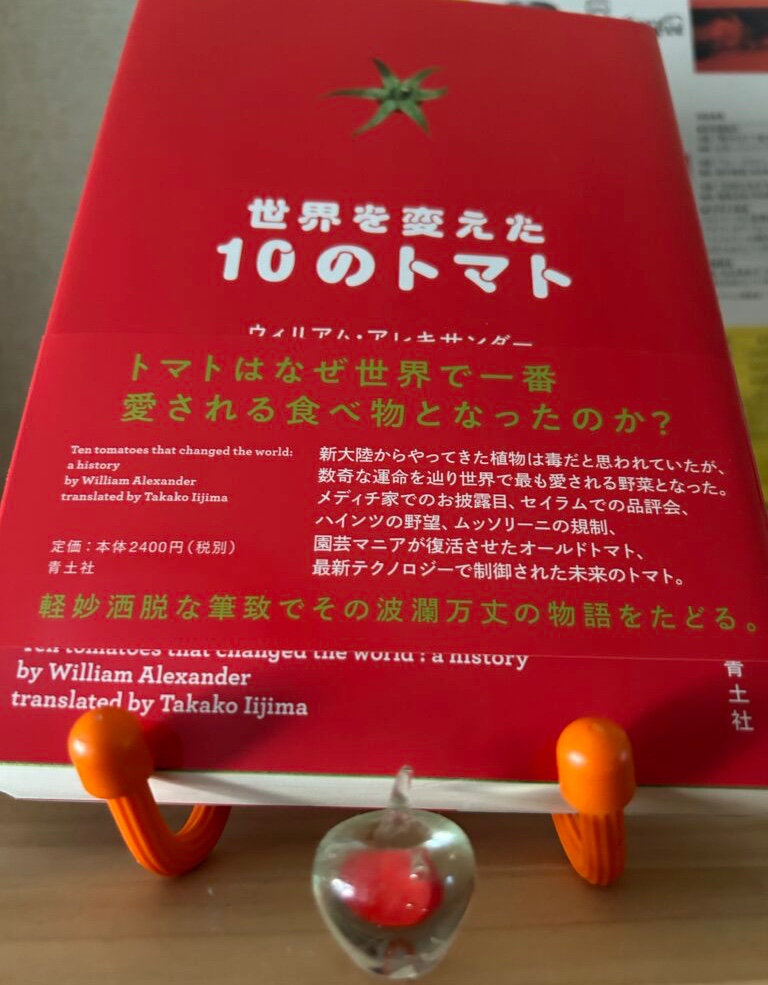
著書[世界を変えた10のトマト](約340ページ)を読み終えて、こんな感じになりました
「トマト…君はどこからきて、そしてどこへ行くのか…」
です、ハイ
さて、あなたはトマトを知っていますか?
あれです
あの赤い感じでみずみずしいアレです
そうです、サルがカニに意地悪するアレです
合ってます、そのトマトです
表紙の赤色が強烈で目に入ったのでゲットしました
毎度のタイトル買いです
ちなみにトマトは好きでも嫌いでもありません。でも、チーズと一緒に放り込むとハイ、サイコーです
そんな最高なトマト
原産地ってどこか知っていますか?
私は「イタリア」と即答したんですが、あなたはどう答えるでしょうか?
ハイ、答えはイタリアではありませんでした
なんなら著者でさえ原産地はイタリアだと思っていたと本の中で語っています
そして
さらにとても大きな事実に驚愕しました
それは
トマトは嫌われものだった
というのです
現在、トマトのことを嫌い、苦手という人はいるでしょう。しかし、それはトマトの味に対しての好き嫌いだと思います
トマトを見かけたら踏みつけて罵りたくなる人はいないんじゃないかと思います
でも、ちょっと前までは散々だったらしいのです
そんなトマトがなぜ嫌われものから世界で最も愛される存在になったのか?
トマトの原産地とはどこなのか?
本の帯にはこう書かれています
「トマトはなぜ世界で1番愛される食べ物となったのか? その波瀾万丈な物語をたどる」
トマトの過去から現在、そして未来をめぐる旅に出ることができる
そんな本でした
まとめ(ジャガイモはトマトのいとこ)
トマトにまつわる人間ドラマ。ここにも宗教と科学のせめぎ合いがある
科学的ではない、その時代その時代の答えにモヤモヤし、それを乗り越えラブアップルとなったトマト
私は人の歴史に興味があるので特にグッときたのがハインツの物語(あのハインツケチャップだ)
読み終えて、スーパーなどでハインツケチャップを見かけると胸が熱くなりニヤつくという後遺症が残ってしまった
あなたはトマトが好きだろうか? 苦手だろうか?
もしあなたが
ぶりっ子「トォムゥァトォゥ〜ってぇ〜。酸ゥッっぱァいィィィからぁ、好きじゃぁなぁいぃいぃ〜」
と、ぶりっ子しているなら、ぜひ本書を手に取ってトマトを知る旅に出てほしい
ぶりっ子がこの本を読み終える頃にはこんな風になっているかもしれない
脱ぶりっ子「ハインツッッ! 君にッ! 敬意を表するッッッ!」
と!
ではッッッ!
※88ページの12行目に[。]が2つ連続してんだが。。←こーなっている
つづく
著書[世界を変えた10のトマト]を読んでみて、知らない用語・人物・文化・歴史などがでてきたので少しでも脳に定着させるために反復します
何かを覚えるということは脳を活性化させ自信を高める効果がある、とかないとか
テキストだけじゃなくイラストもあるとより覚えやすい、とかなんとか
よかったらあなたも一緒に脳に定着させませんか?
興味がありましたらお付き合いください
※本の内容には一切触れません。あくまで歴史・文化・建造物・偉人などの共通の事実と思われるものをインプットし、アウトプットするためのものです。ここから記載するのは、私が私なりに得た知識を別でも検索した結果、共通の事実であることと判断したもののみを記載します。著者の表現などは一切記載しませんが、[私なりの事実の検索]が不十分なこともあるかもしれません
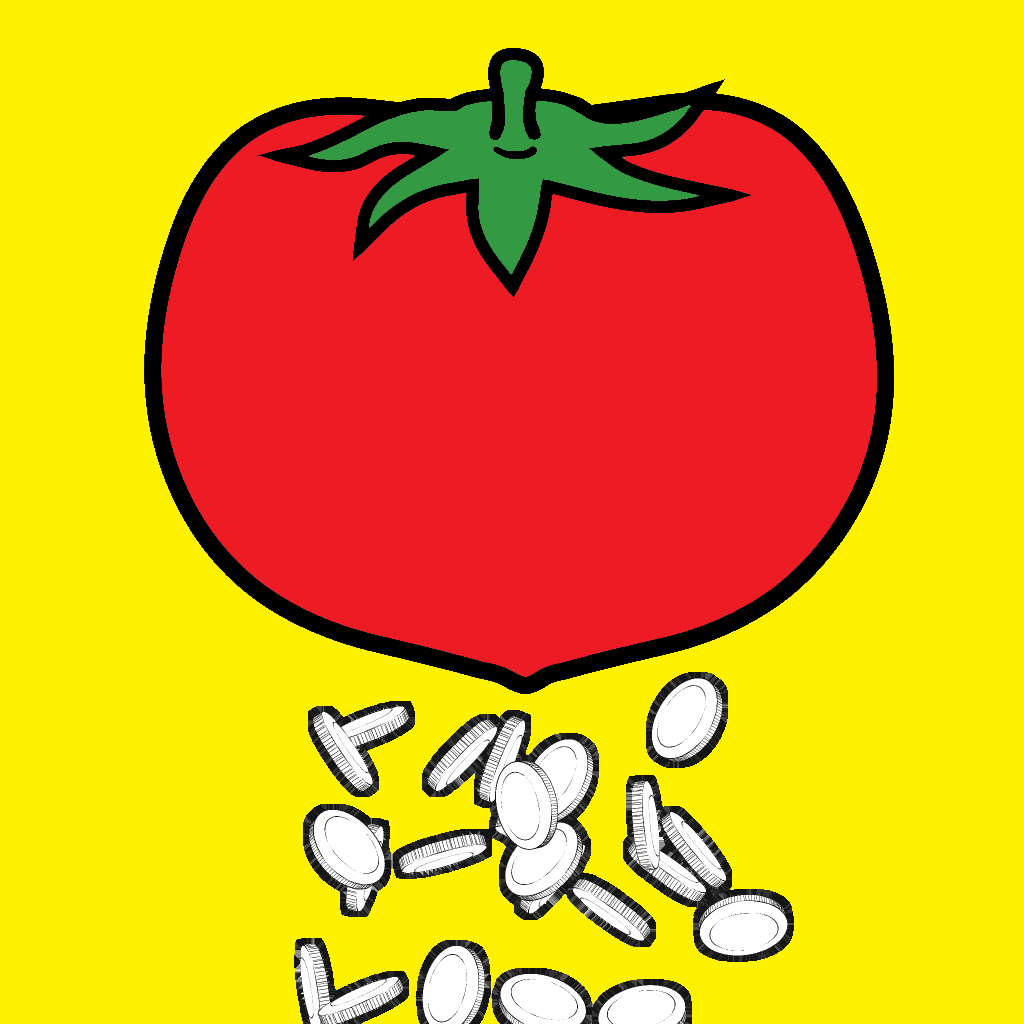
テノチティトラン(Tenochtitlan)
現在のメキシコシティの地下に位置する14世紀半ば〜16世紀初頭にかけて繁栄したアステカ帝国の首都。当時のアステカ帝国は湖の上にポツンとあった、現在は陸続き
ピサ大聖堂(1118年完成)
11世紀にパレルモ沖海戦に勝利した記念にピサのドゥオモ広場に建設された建造物。現在は世界遺産、観光地
ピサの斜塔
ピサ大聖堂と同じ広場に建造された鐘楼(検索したら営業時間の情報がでてきた。20時までらしい)当時はヨーロッパ最大の塔
子室(ししつ)
トマトのゼラチン質の柔らかい部分のこと
カルロ・コッローディ(Carlo Collodi)
ピノキオの原作者、イタリアの児童文学作家。1881~1882年にピノッキオの冒険を連載。本名はカルロ・ロレンツィーニ(Carlo Lorenzini)、コッローディーはペンネーム、発音が難しい
サミュエル・モールス
スパゲッティの語源はイタリア語で[紐]
ファルファッレ(Farfalla、リボン型のパスタ)の語源はイタリア語で[蝶]
ヴェルミチェッリ(Vermicelli、ちょい太麺のパスタ)の語源はイタリア語で[ミミズ]
調べてみたらヴェルミチェッリは伝統のパスタとあったけど、その語源がなぜにミミズ? 紐、蝶ときてミミズ…益虫が関係してるのかな
ポリガラクツロナーゼ(PG)
トマトがシワシワになっていく現象を引き起こすもの、なのか? 調べたけど硬い情報しか出てこなかったので目を閉じた
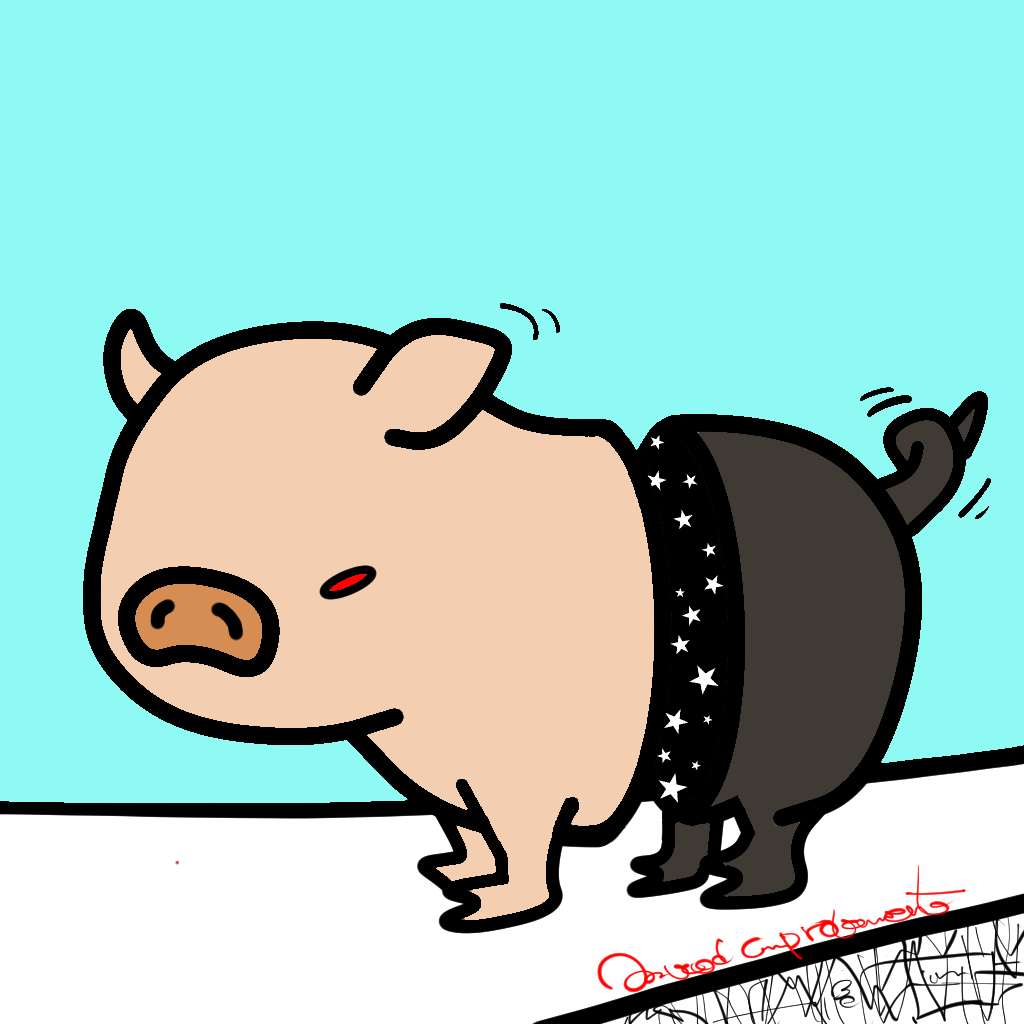
つづく